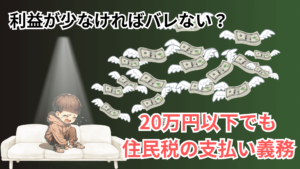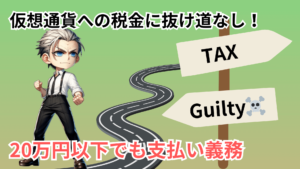法人で仮想通貨を保有すると税金はどうなる?含み益課税と改正ポイント
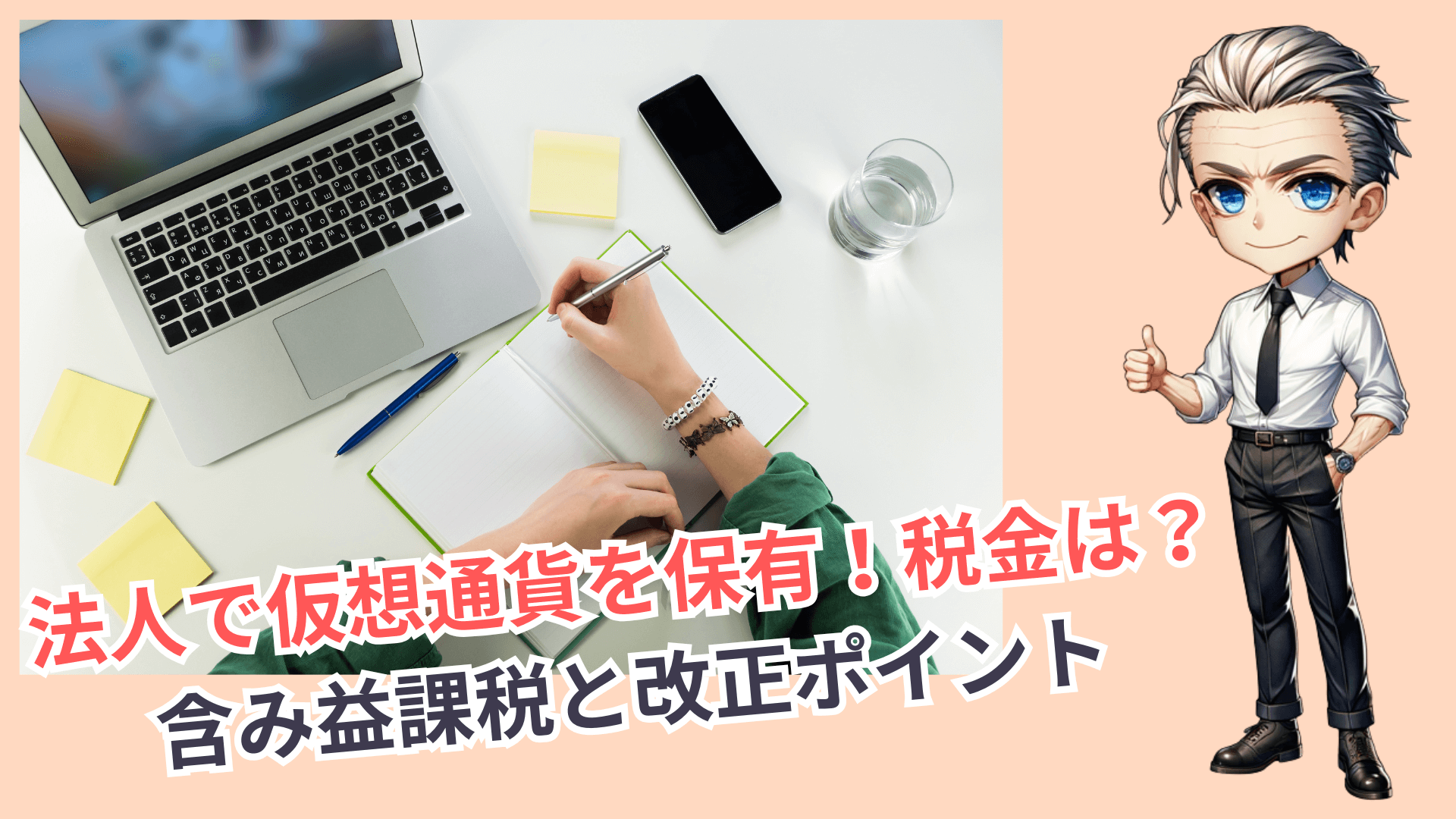
法人が仮想通貨を持つと、持っているだけで税金がかかるの?
個人より法人のほうが税金は安くなるの?
小さな会社でも仮想通貨を持っていいの?
法人が仮想通貨を持つと、売っていなくても決算時の評価額で課税されることがあります。
この記事では、含み益課税の仕組みや税制改正のポイント、小さな会社が安全に始めるためのコツをわかりやすく解説します。

これからフリーランスになる人にもおススメだ!
- 決算時に値上がりしていれば課税対象です。(売っていなくても)
- 利益が大きい場合は、法人の方が税率が低く有利です。
- 可能です。まずは少額で税金の動きを確認しましょう。
法人が仮想通貨を持つと何が課税対象になるのか?
期末時価評価と含み益課税の仕組み
法人が仮想通貨を保有している場合、決算期ごとに「時価評価」を行い、評価益が出ていれば課税対象となります。
個人投資家と異なり、法人は「期末時点での含み益」にも法人税がかかるため、持っているだけで利益が確定したとみなされる点に注意が必要です。
イメージすると「まだ売ってないゲームのレアカード」でも、会社の場合は
『このカードいま5万円で売れるよね?じゃあ5万円得したってことにして税金ちょうだいね』
と言われる感じです。手元に現金は増えてないのに請求だけは来るイメージです。
| タイミング | 仮想通貨評価額 | 帳簿上の利益(評価益) | 課税される? |
|---|---|---|---|
| 購入時 | 100万円 | 0円 | されない |
| 決算日(まだ売ってない) | 150万円 | 50万円 | される(法人) |
法人は「持っているだけの値上がり」も課税対象になることがある。
個人の場合との違い(雑所得・総合課税)
個人は売却・交換などで利益が確定したタイミングで課税され、含み益には課税されません。
つまり、法人は「評価時点課税」、個人は「実現時課税」であり、この違いが大きな税負担差を生みます。
たとえ話にすると、個人は「メルカリで本当に売れたお金」に税金がかかる。
法人は「メルカリに出したらすぐ売れるでしょ、その値段でもう儲かったことにしよう」と言われる感じです。
| 項目 | 個人(会社員・副業など) | 法人(会社名義) |
|---|---|---|
| いつ課税? | 売った/使ったタイミング | 決算時の評価額でも課税対象になることあり |
| 含み益(まだ売ってない値上がり) | 課税されない | 課税対象になることがある |
| 税金の扱い | 雑所得などで総合課税 | 法人税の計算に入る |
令和6年税制改正のポイント
法人に有利になった改正内容
令和6年度の税制改正で、一定の条件を満たす自社保有トークン(第三者に譲渡できない暗号資産)は、期末評価課税の対象外になりました。
これにより、Web3企業や独自トークンを発行する法人は、評価益課税を避けやすくなり、事業リスクが軽減されています。
かみ砕いて話すと
「お店の中だけで使えるポイント券」が高く評価されても、『それはまだ本当のお金ってことにしなくていいよ』と国が言ってくれたイメージです。
企業が “すぐ第三者に自由に売れない” 独自トークンを発行している事例として、以下があります。
- フィナンシェ(トークン型クラウドファンディング) — ファン向けのトークン発行を行い、応援・特典付きの仕組みを提供。FiNANCiE(フィナンシェ)+2meta.japanstep.jp+2
- SBIホールディングス(独自トークン発行によるプラットフォーム展開) — 「独自トークンを発行し、宿泊・飲食・買物などのサービスに利用できる」という発表あり。SBIグループ
- JPYC株式会社(ステーブルコイン/トークン発行事業) — トークンやステーブルコインの発行・活用事業を手がけている会社。JPYC株式会社
個人より法人を選ぶメリットが増えたケース
法人は実効税率が約23〜30%前後で、個人の最大55%より低く抑えられるため、高利益を見込むなら法人の方が有利です。
さらに欠損金の繰越控除が可能で、翌年度以降の利益と相殺できる点も、長期的な節税メリットにつながります。
これは個人にはない大きな魅力で
法人は「前のテストで悪かった点数を次のテストの点数と合算できる」。個人は「テストはテスト、その時の点数で即評価される」状態です。
| 年間の仮想通貨の利益額イメージ | 個人側のイメージ(累進で最大かなり高い) | 法人側のイメージ(20〜30%台で安定しやすい) |
|---|---|---|
| 50万円 | 人による(ほかの収入と合算で税率決定) | 多くの場合20〜30%台の範囲 |
| 1,000万円 | 人によっては50%近いラインまでいくこともある | おおむね30%前後に収まることが多い傾向 |
※ ここでは「個人は累進課税」「法人は法人税ベース」という基本イメージとしてとらえてください。
実際に課税が発生するタイミング
利益確定時の課税
仮想通貨を売却・交換・決済に使った瞬間に利益が確定し、その時点の時価で課税対象になります。
たとえば、購入額100万円→売却額150万円なら、50万円が課税所得として扱われます。
| 行動 | 何が起きた? | 課税される? |
|---|---|---|
| ビットコインを買う | 100万円払って保有開始 | まだ課税されない |
| 値上がって150万円相当になる | 含み益50万円が発生 | 法人は決算で評価→課税に入る可能性あり |
| 売る/使う | 150万円相当で手放す →50万円の利益確定 | 課税対象になる |
含み益課税の注意点
含み益課税は、実際に利益を得ていなくても「帳簿上の利益」として計上されるため、キャッシュフロー上の負担が発生します。
評価損が出た場合には損金として処理できますが、短期的な値下がり局面では利益確定タイミングの調整が重要です。
たとえると、ゲーム内アイテムが突然レアになって「君は今すごいお金持ち!入場料(税金)払って」と言われるけど、そのアイテムまだ売ってないから現金がない…という状態です。
リスクが出る典型パターン(資金繰りが苦しくなる例)
| 状況 | 現金残高 | 仮想通貨の評価額 | 帳簿上の利益(評価益) | 起きる問題 |
|---|---|---|---|---|
| 決算直前に仮想通貨が急騰した | 100万円 | 300万円 | +200万円 | 税金は発生するのに、支払う現金は100万円しかなくて苦しい |
法人が取るべき対策
税理士・会計ソフトの活用
仮想通貨の評価や損益計算は複雑なため、暗号資産に対応した会計ソフトや税理士との連携が必須です。
特にfreeeやマネーフォワードなどでは法人対応プランがあり、評価損益や仕訳を自動計算できる機能が充実しています
最低限チェックすべきところ
| チェック項目 | なぜ大事? |
|---|---|
| 購入・売却の日時・金額を記録しているか | どこからどこまでが「利益」か説明できる必要がある |
| 決算日時点の評価額がわかるか | 含み益課税の対象かどうか判断する材料になる |
| 勘定科目の整理ができているか | 決算書・申告書で突っ込まれたときに答えられる |
CryptoLinC(クリプトリンク)がとてもおススメです。


| 正確・安心 | 計算をラクに | 節税サービス |
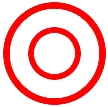 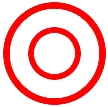 税理士が開発したツール! | 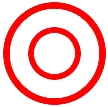 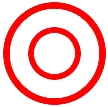 複数の取引所データを簡単計算! | 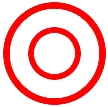 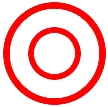 税理士に相談できる! |
- 仮想通貨専門の税理士が開発したツールで、同じ税理士界隈から圧倒的支持!
- 海外取引所を含む複数の取引所の損益計算がcsvで速く正確に!
- 節税対策をされたい方向けに税理士への相談が可能!
\ 税理士に選ばれるツール /
登録5分で無料ではじめる
小規模から始める工夫
まずは小額運用で「評価課税の影響」を試し、リスクを把握したうえで投資規模を広げるのが安全です。
大きな金額を一度に投入すると、年度末に思わぬ税負担が生じるため、分散購入やタイミング調整も効果的です。
スタート戦略の違い
| スタイル | やり方のイメージ | リスク |
|---|---|---|
| いきなり全額投下型 | 最初から数百万円ドンと買う | 決算時の含み益課税で納税資金が足りなくなる恐れ |
| 小さくテスト型 | まずは数十万円レベルで様子を見る | 税金インパクトと運用フローを把握しながら拡大できる |
小さな会社やフリーランス法人はどう活用すべきか?
少人数の会社やフリーランス法人は、いきなり多額を投じず、まず「事業との関連性」と「資金繰りの安全性」を重視して始めるのが現実的です。
法人化のメリット(税率・損益通算)は魅力的でも、資金繰りを崩すと意味がありません。
まずは少額運用や積立型購入で“評価益課税”がどれくらい発生するか体験し、顧問税理士や会計ソフトで数字を見える化してから拡大を検討しましょう。
まとめ
法人が仮想通貨を保有すると、含み益にも課税される点が大きな特徴です。
令和6年改正で一部は緩和されましたが、小規模法人は資金繰りを見ながら慎重に活用することが重要です。